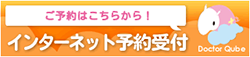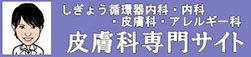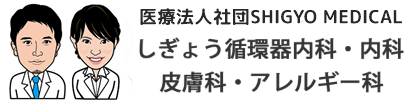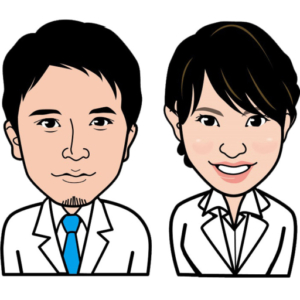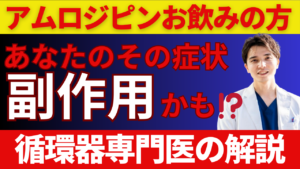それは“脅し”ではなく、“最後の分かれ道”かもしれません
「このままだと透析になりますよ」。
医師からそう言われて、胸が詰まるような思いをされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。「本当にそんなに悪いの?」「脅かされているだけじゃないの?」と戸惑う気持ちも、よくわかります。
でも、私たち糖尿病専門医がこの言葉を口にするのは、患者さんを責めるためでも、怖がらせるためでもありません。むしろ、これ以上腎臓を悪くしないための“最後の分かれ道”に差しかかっていることを真剣にお伝えしたいのです。
そして何より大切なのは、透析が決まったわけではないということ。今ここで気づき、真剣に向き合い始めれば、まだ腎臓を守れる可能性は十分にあるんです。
「尿たんぱくが出ています」…それは腎症の静かな始まり
健康診断やかかりつけ医で「尿たんぱくが出ていますね」と言われた経験はありませんか? けれど体に異変は感じず、「気にしなくてもいいかも」と放置してしまう方も多いのが実情です。
しかし、この「尿たんぱく」、特に「微量アルブミン尿」と言われる初期段階は、糖尿病性腎症のはじまりを示す非常に重要なサインです。
血管の塊である腎臓で血管がダメージを受け始めると、たんぱく質が尿中に漏れ出すようになります。これは、腎臓の働きが悪くなっている証拠なのです。
この段階であれば、生活習慣の改善や医師との連携で進行を食い止めることが可能です。逆に、「症状がないからまだ大丈夫」と思ってしまうと、静かに、しかし確実に腎機能は悪化していきます。
腎臓は「段階的に」静かに傷んでいきます
糖尿病性腎症は、次のような段階で進行していきます。
- 第1期:腎症前期(見た目の異常なし)
- 第2期:早期腎症期(微量アルブミンたんぱく尿が出始める)
- 第3期:顕性腎症期(明らかな尿たんぱくが出て量が増えていく)
- 第4期:腎機能低下期(血液検査でも異常がはっきり)
- 第5期:末期腎不全期(人工透析や腎移植が必要)
この進行は、ある日突然起こるわけではありません。静かに、気づかれないまま、年月をかけて腎臓は少しずつ傷んでいきます。
ですから、検査で何らかの異常が見つかったときこそが、進行を食い止める貴重なチャンスです。このチャンスを逃さず、必要な対策をとることが、将来の透析を回避するための第一歩です。
透析になる人、ならない人の違いとは?
透析治療者は年々増え続け、その多くは糖尿病を原因とする腎症によるものです。
しかし、すべての糖尿病患者さんが透析になるわけではありません。ここに、大きな「違い」があります。
透析に至った方の中には、血糖値が高い状態を長年放置していた方や、血圧をしっかり管理できていなかった方、食生活に無頓着だった方が多く見られます。また、通院を途中でやめてしまったケースも珍しくありません。
一方、透析を免れている方々の多くは、医師との連携を保ちながら、血糖値・血圧・塩分・水分・食事の管理などを日々の生活の中でしっかり意識しておられます。決して特別な治療をしているわけではありません。ただ、小さな注意を積み重ねているのです。
どれだけ進行していても「今からできること」があります
「クレアチニンが上がってしまった」「eGFRが60を切ってしまった」「尿たんぱくが持続している」……。
こんな状況になっていても、「もう手遅れだ」とは思わないでください。これ以上悪くしない努力は、どんな段階でも可能です。
血糖や血圧の管理を今からでも整える。塩分を控え、水分、食事や生活習慣を見直す。処方薬の見直しを医師と相談する。
70代の男性患者さんで、腎機能(eGFR)が低下していた方が、半年間しっかり取り組むことで、腎機能の悪化を止められたケースがあります。「透析を覚悟していたが、もっと早くに正確な自分の状態と対応方法を知りたかった」とおっしゃっていたのが印象的でした。
今日から始められる、腎臓を守る習慣
まず大切なのは、血糖と血圧の目標値を意識することです。HbA1cは7.0%未満を目安としながらも目標は個別に設定します。血圧は診察室の血圧130/80mmHg未満、家庭血圧125/75mmHg未満を目指します。血圧を下げる薬は主に腎臓を保護する作用を持つ薬(ARBやACE阻害薬)を使います。
食事では、1日6g未満の減塩を意識しましょう。汁物や加工食品、外食などは塩分が多くなりがちなので、工夫が必要です。出汁のうま味や酸味、香辛料を活用すれば、減塩でも美味しく満足できる食事が作れます。
水分も大切な要素です。腎臓や心臓に大きな問題がなければ、1日1.0~1.5リットルを目標に水分を摂りましょう。脱水状態は腎臓の血流を減らし、負担をかけます。
喫煙は腎機能低下を加速させる最大の生活習慣リスクのひとつです。もしタバコを吸っているなら、腎臓のために禁煙を真剣に考えましょう。
検査値を「知る」ことが、あなたの未来を守ります
腎機能を見る代表的な検査値には、eGFR、クレアチニン、尿アルブミン/クレアチニン比などがあります。これらの意味を患者さんご自身が理解しているかどうかで、治療への意識が大きく変わります。
たとえばeGFRは、腎臓の“ろ過力”を示す数値。60以上で正常とされますが、50台、40台と下がるにつれて、徐々に腎臓の働きも落ちていることになります。
クレアチニンは腎機能の低下で上がる値ですし、尿アルブミンは腎臓の血管がどの程度傷ついているかを早期に知る指標です。
これらは単なる「数値」ではありません。あなたの未来を守るための“地図”なのです。だからこそ、定期的に確認しながら、必要に応じて軌道修正していきましょう。
最後に ― まだ間に合います
透析は、人生の終わりではありません。けれど、できることなら避けたい――それが本音だと思います。
「尿たんぱくが出た」「腎機能が悪いと言われた」
そんな今こそが、腎臓を守る“最後のチャンス”かもしれません。どうか一人で抱え込まず、あなたの不安をそのまま私たちにお話しください。
あなたに今、必要なのは「医学的に完璧な生活」ではありません。
少しの意識、少しの習慣、少しの行動。
その積み重ねが、将来の透析を防ぐ大きな力になるのです。
私たちは、その積み重ねを全力でサポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
参考文献
- 日本糖尿病学会編. 『糖尿病診療ガイドライン2024』. 南江堂, 2024.
- 日本腎臓学会編. 『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』. 東京医学社, 2023.
- KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2022;102(5S):S1-S127.
- 厚生労働省. 「慢性腎臓病(CKD)」e-ヘルスネット. https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp
- 日本透析医学会. 「わが国の慢性透析療法の現況(2022年12月31日現在)」. https://docs.jsdt.or.jp/overview/