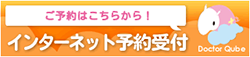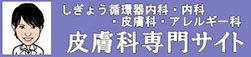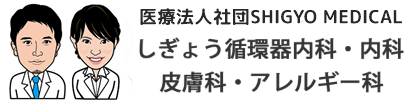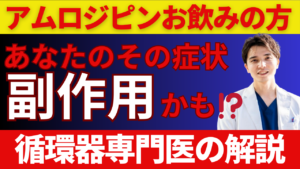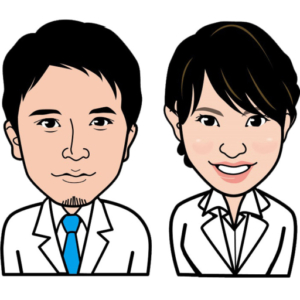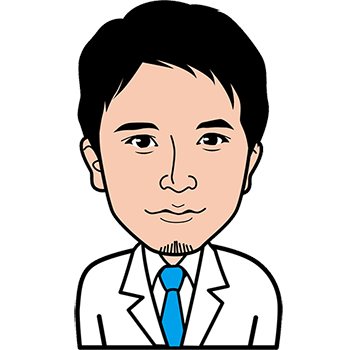 しぎょう院長
しぎょう院長こんにちは。循環器専門医のしぎょうです。
あなたはいつも左右でどちらか血圧が低く
「本当に正しい血圧はどちらなの?」と思っていませんか?
今回は血圧の左右差についてご説明します。


はじめに
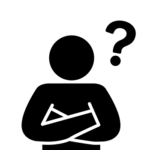
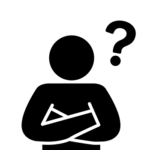
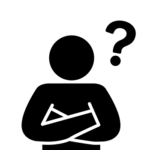
「右と左で血圧が違うんですが、大丈夫でしょうか?」
循環器内科の外来で、非常によく受ける質問です。家庭で血圧を測定している方の多くが、一度は左右差を経験し、不安を感じたことがあるのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、多くの場合、血圧の左右差は測定タイミングの違いによる自然な変動です。しかし、常に10mmHg以上の差が続く場合には、血管の病気が隠れている可能性があり、注意が必要です。
本記事では、血圧の左右差が生じるメカニズム、心配のいらないケースと受診が必要なケースの見分け方、正しい測定方法、そして左右差が示唆する疾患について、エビデンスに基づいて詳しく解説します。
血圧の左右差はどのくらい普通なのか?
健常者でも左右差は存在する
血圧は非常に変動しやすい生体指標です。呼吸、姿勢、会話、精神的緊張など、さまざまな要因で数分の間に5〜10mmHg程度は容易に変動します。
大規模研究によると、健常者においても片腕ずつ測定した場合、収縮期血圧(上の血圧)で5〜10mmHgの左右差が認められることは珍しくありません。これは、測定する順番による時間差、腕の位置の微妙な違い、血管の個人差などが影響しているためです。
「同時測定」と「順番測定」の違い
重要なのは、同時に両腕を測定したか、それとも順番に測定したかという点です。
家庭用血圧計で一般的な「片腕ずつ測る方法」では、最初の測定から次の測定までに1〜2分以上の時間差が生じます。この間に血圧は自然に変動するため、左右差の多くは実際の血管の問題ではなく、測定タイミングのズレによるものなのです。
実際、同時に両腕の血圧を測定した研究では、健常者の左右差の平均は収縮期血圧で約3〜5mmHg程度であることが示されています。
いつ医療機関を受診すべきか?
10mmHg以上の持続的な左右差は要注意
日本高血圧学会のガイドラインおよび国際的なエビデンスでは、収縮期血圧で10mmHg以上の左右差が繰り返し認められる場合、末梢動脈疾患や心血管イベントのリスクが高いことが報告されています。
具体的には、以下のような場合に医療機関での精査をお勧めします。
受診を検討すべきケース:
- 何度測定しても、常に片方の腕が10mmHg以上高い(または低い)
- 左右差が徐々に拡大してきている
- 腕のしびれ、冷感、脈の弱さを伴う
- 歩行時の足の痛みやだるさがある
- 高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙歴などの動脈硬化リスクがある
なぜ10mmHgが基準なのか?
大規模なメタアナリシスでは、収縮期血圧の左右差が10mmHg以上ある人は、末梢動脈疾患の有病率が約2.5倍、10年以内の心血管死亡リスクが約1.6倍高いことが示されています。
この10mmHgという数値は、単なる測定誤差を超えて、実際の血管狭窄を反映している可能性が高い閾値として、国際的に認識されています。
血圧の左右差が示唆する疾患
持続的な左右差がある場合、以下のような血管疾患が背景に存在する可能性があります。
1. 鎖骨下動脈狭窄症
鎖骨下動脈は、心臓から出た大動脈から分岐して腕に血液を送る太い血管です。動脈硬化によってこの血管が狭くなると、その先にある上腕動脈での血圧が低下します。
特徴:
- 狭窄がある側の腕の血圧が低く測定される
- 腕のだるさ、冷感、運動時の疲労感
- 脈拍が弱い、または触れにくい
- めまいや失神(鎖骨下動脈盗血症候群の場合)
鎖骨下動脈狭窄症は、全身の動脈硬化が進行しているサインでもあり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクも高い状態です。
2. 大動脈炎症候群(高安動脈炎)
比較的若い女性(20〜40歳代)に多い、大動脈やその分枝に炎症が起こる疾患です。
特徴:
- 著しい血圧の左右差(20mmHg以上のことも)
- 脈が触れにくい(「脈なし病」とも呼ばれる)
- 全身倦怠感、微熱、体重減少
- 視力障害やめまい
早期診断と適切な治療(ステロイドや免疫抑制剤)が重要で、放置すると血管閉塞や動脈瘤破裂などの重篤な合併症を引き起こします。
3. 閉塞性動脈硬化症(ASO)
主に下肢の動脈が狭窄・閉塞する疾患ですが、上肢にも動脈硬化が及んでいる場合があります。
特徴:
- 喫煙、糖尿病、高血圧などのリスク因子を持つ
- 歩行時のふくらはぎの痛み(間欠性跛行)
- 足の冷感、しびれ、傷が治りにくい
- 全身の動脈硬化が進行している
ASOがある方は、心筋梗塞や脳梗塞のリスクも非常に高く、包括的な心血管リスク管理が必要です。
4. 大動脈解離・大動脈瘤
急性大動脈解離では、血流の経路が変化するため、急激な血圧の左右差が出現することがあります。
特徴(緊急性が高い):
- 突然の激しい胸痛・背部痛
- 著しい血圧の左右差(15〜20mmHg以上)
- 意識障害、失神
- 脈拍の左右差
このような症状がある場合は、直ちに救急医療機関を受診してください。
正しい血圧測定方法
左右差を正確に評価するためには、正しい測定方法を理解することが不可欠です。
基本的な測定手順
環境の整備:
- 静かで適温の部屋で測定する
- 測定前5分間は安静にする
- 測定前30分以内の喫煙、カフェイン摂取は避ける
正しい姿勢:
- 背もたれのある椅子に深く腰掛ける
- 足を組まず、床にしっかりつける
- 腕を心臓の高さ(机の上など)に置く
- リラックスし、会話を避ける
カフの装着:
- 素肌に直接巻く(厚手の服の上は不可)
- カフの下縁が肘の2〜3cm上
- 指1〜2本分の余裕がある程度の締め具合
左右差の確認方法
初回評価:
- まず右腕で2回測定し、平均値を記録
- 2〜3分の間隔をあけて左腕で2回測定し、平均値を記録
- 左右の平均値を比較
日常測定:
- 左右差が5mmHg以内であれば、どちらの腕で測定しても可
- 10mmHg以上の差がある場合は、常に高い方の腕で測定
- 週に1〜2回程度、左右差を再確認することも有用
よくある測定ミス
腕の高さが不適切:
- 腕が心臓より低いと血圧は高めに出ます(5〜10mmHg程度)
- 腕が心臓より高いと血圧は低めに出ます
カフのサイズが合っていない:
- 腕が太い方に標準カフを使うと高めに出ます
- 腕が細い方に標準カフを使うと低めに出ます
連続測定による誤差:
- 連続して何度も測ると、うっ血により血圧が変動します
- 少なくとも1〜2分の間隔をあけましょう
医療機関での検査
持続的な左右差が認められる場合、以下のような検査が行われます。
ABI(足関節上腕血圧比)検査
両腕と両足の血圧を同時に測定し、下肢の動脈硬化や狭窄を評価する検査です。
正常値: ABI > 0.9
異常値: ABI ≤ 0.9(末梢動脈疾患を示唆)
簡便で非侵襲的な検査であり、動脈硬化のスクリーニングに有用です。
血管エコー検査
超音波を用いて、鎖骨下動脈、上腕動脈、大動脈などの血管の狭窄や血流を直接観察します。
評価できる項目:
- 血管の狭窄の有無と程度
- 血流速度の変化
- プラーク(動脈硬化巣)の存在
- 血管壁の厚さ
CT・MRI血管造影
より詳細な血管の形態評価が必要な場合に行います。大動脈炎症候群や大動脈解離の診断にも有用です。
左右差がある場合の対処法
どちらの腕で測定すべきか?
国際的なガイドラインでは、常に高い方の腕で血圧を測定することが推奨されています。
理由は以下の通りです:
- 低い方の腕は血管狭窄により実際より低く測定されている可能性がある
- 高い方の値が、体全体の真の血圧をより正確に反映している
- 治療目標の設定や降圧薬の調整は、真の血圧に基づいて行うべき
まとめ
血圧の左右差は、多くの場合、測定タイミングのズレや測定方法の誤差によるものです。健常者でも5〜10mmHg程度の左右差は珍しくありません。
しかし、何度測定しても常に10mmHg以上の左右差が続く場合は、血管の狭窄や動脈硬化を示唆する重要なサインの可能性があります。このような場合は、循環器内科を受診し、適切な検査を受けることをお勧めします。
重要なポイント:
- 左右差の多くは測定誤差であり、過度に心配する必要はない
- 持続的な10mmHg以上の差は医療機関で精査が必要
- 高い方の腕で測定するのが原則
- 正しい測定方法を身につけることが大切
- 動脈硬化リスクがある方は特に注意深い観察が必要
血圧測定は、血管の健康状態を知るための重要な手段です。小さな変化にも目を向けながら、適切な対応を心がけることで、重大な心血管疾患の予防につながります。
気になる症状や持続的な左右差がある場合は、早めに専門医にご相談ください。
参考文献
- Clark CE, et al. Association of a difference in systolic blood pressure between arms with vascular disease and mortality: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2012;379(9819):905-914.
- Clark CE, et al. Prevalence of systolic inter-arm differences in blood pressure for different primary care populations: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012;344:e1327.
- 日本高血圧学会. 高血圧治療ガイドライン2019(JSH2019)
- Whelton PK, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. Hypertension. 2018;71(6):e13-e115.