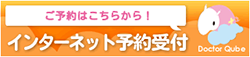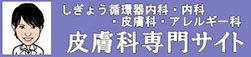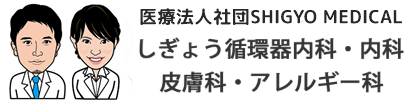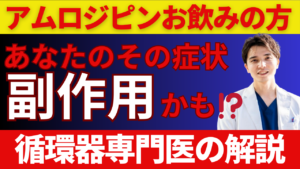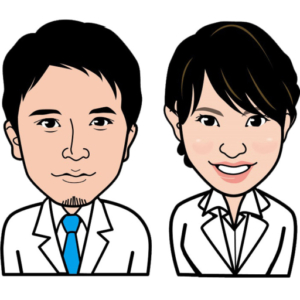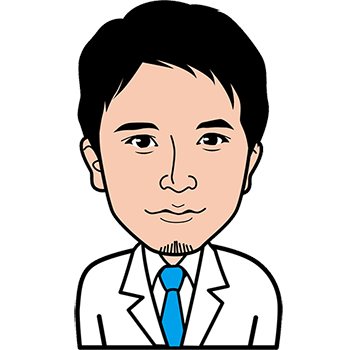 しぎょう院長
しぎょう院長こんにちは、循環器専門医のしぎょうです。本日は検診での脂肪肝を指摘されてほったらかしの人が結構多いので実は肝臓も大事だけど動脈硬化が進行しているかもということを伝えたくて筆をとりました。
あなたは健康診断で「脂肪肝」と診断されたことありませんか?「症状もないし、肝臓の問題だから」と放置していませんか?
脂肪肝は、実は動脈硬化の進行を示す重要なサインです。無症状だからと放置することで心筋梗塞や脳卒中といった致命的な循環器疾患のリスクが高まります。
意外かもしれませんが、脂肪肝と診断された方の多くは、肝臓疾患ではなく心臓血管疾患で亡くなっています。
この記事では、脂肪肝と動脈硬化の密接な関係について解説し、健康診断で「脂肪肝」と言われたら何をすべきかを簡単にお伝えします。あなたの命を守るために、ぜひ最後までお読みください。


脂肪肝の見えない脅威
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれています。肝臓が悲鳴を上げても、痛みなどの症状がほとんど現れないためです。脂肪肝は、肝臓の細胞に中性脂肪が過剰に蓄積した状態で、日本人成人の約3割が該当すると言われています。特に40代以降の男性や閉経後の女性に多く見られます。
健康診断で「脂肪肝」と診断されても、「特に治療は必要ありません」「食事に気をつけてください」と言われるだけで終わることが多いのではないでしょうか。しかし、この「様子見」が命取りになる可能性があるんです。
知られざる真実、脂肪肝患者の死因は肝臓ではない!
国立国際医療研究センターの調査によると、脂肪肝患者の主な死因は実は肝疾患ではないんです。脂肪肝と診断された患者の追跡調査では、死亡原因の第1位は心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患(全体の35%)、第2位ががん(28%)で、肝疾患による死亡はわずか4%に過ぎませんでした。
つまり、脂肪肝と診断された方の多くは、肝臓の問題が直接命を奪うのではなく、気づかないうちに進行している動脈硬化疾患によって命を落としているんです。
しかし検診で、脂肪肝と診断された場合、消化器あるいは肝臓専門医の受診を推奨します。そうなると肝臓に関してはしっかりと検査してくれますが、循環器系のリスク評価が行われないことが多いんです。つまり肝臓と血管の関係性は、肝臓専門医だけでなく循環器専門医の視点でも見ないとリスクが見落とされてしまいます。
脂肪肝が動脈硬化を加速させる恐ろしいメカニズム
インスリン抵抗性
脂肪肝と動脈硬化には共通の敵がいます。それは「インスリン抵抗性」です。インスリン抵抗性とは、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの効きが悪くなった状態です。
インスリン抵抗性が進むと、血中の糖や脂質が増加し、肝臓に脂肪が蓄積するとともに、血管壁にもダメージを与えます。血管壁の内側にある内皮細胞の機能が低下すると、そこから脂質が侵入し、炎症反応が起こります。これが動脈硬化の始まりです。
脂肪肝からの有害物質の放出
脂肪肝になると、肝臓は様々な炎症性物質を血液中に放出します。TNF-α(腫瘍壊死因子α)やIL-6(インターロイキン6)などの炎症性サイトカインは、直接血管壁にダメージを与え、動脈硬化をさらに進めます。
また、脂肪肝の肝細胞からは異常なリポタンパク質が産生され、血管壁に沈着しやすくなります。これが「悪玉コレステロール」として知られるLDLの質的異常を引き起こし、さらに動脈硬化を加速させます。
このように動脈硬化が進むと、今度は全身の血流が悪くなり、肝臓への血流も減少します。肝臓への血流が減少すると肝細胞はさらにダメージを受け、より多くの有害物質を放出するようになり悪循環が加速していきます。
こういった状況になっていても脂肪肝はほとんど自覚症状がなく静かに進行します。脂肪肝の診断から10年以内に、約30%の患者が何らかの心血管イベント(心筋梗塞や狭心症など)を経験するという研究結果もあります。特に、ALT(GPT)やγ-GTPなどの肝機能値が正常でも、脂肪肝があれば動脈硬化のリスクは上昇しているのです。
脂肪肝と動脈硬化から身を守る具体的な方法
まずは総合的な検査を受けよう
脂肪肝と診断されたら、単に「様子を見る」のではなく、循環器系の評価も受けることが重要です。具体的には以下の検査を検討しましょう:
- 頸動脈エコー検査:首の血管の状態を調べ、動脈硬化の程度を評価します。
- ABI(足関節上腕血圧比)検査:手と足の血圧を比較し、末梢動脈疾患のリスクを評価します。
- 心電図・心エコー検査:心臓の状態や機能を評価します。
- 血液検査:脂質プロファイル(LDL、HDL、中性脂肪など)、血糖値、HbA1c、高感度CRPなどの炎症マーカーを調べます。
これらの検査は、多くの総合病院や循環器クリニックで受けることができます。かかりつけ医に相談し、適切な医療機関を紹介してもらいましょう。
生活習慣の改善で両方の問題に対処
脂肪肝と動脈硬化は共通の原因から生じるため、生活習慣の改善によって両方に同時に対処できます:
- 適正体重の維持:体重の5-10%減量するだけでも、脂肪肝と動脈硬化の進行を抑制できます。
- バランスの取れた食事:
- 果物や野菜、全粒穀物、豆類などの食物繊維が豊富な食品を積極的に摂取
- 飽和脂肪やトランス脂肪の摂取を控える
- 砂糖や精製炭水化物の摂取を減らす
- オメガ3脂肪酸(青魚、亜麻仁油など)を適度に摂取
- 定期的な運動:週に150分以上の中等度の有酸素運動(速歩、水泳、サイクリングなど)と、週に2回以上の筋力トレーニングが理想的です。
- 禁煙・適量の飲酒:喫煙は動脈硬化を促進し、過度の飲酒は脂肪肝を悪化させます。
適切な薬物療法
生活習慣の改善だけでコントロールが難しい場合は、薬物療法を検討することも重要です:
- スタチンなどの脂質降下薬:LDLコレステロールを下げ、動脈硬化の進行を抑制します。肝臓への負担を心配する声もありますが、適切な管理のもとでは脂肪肝患者にも安全に使用できることが多くの研究で示されています。
- 糖尿病治療薬:メトホルミンやSGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬などは、血糖コントロールだけでなく、脂肪肝の改善にも効果があることが報告されています。
よくある誤解
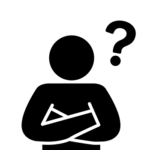
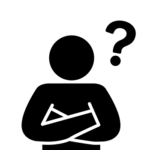
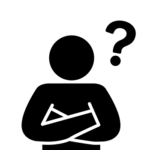
「肝機能値が正常なのに、本当に検査が必要?」
肝機能値(ALT、AST、γ-GTPなど)が正常範囲内であっても、脂肪肝自体が動脈硬化のリスク因子であることが研究で示されています。実際、肝機能値が正常な「非アルコール性脂肪肝」の患者さんでも、心血管疾患のリスクは非脂肪肝の方と比べて約1.5倍高いことが報告されています。
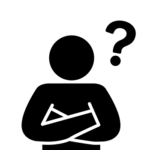
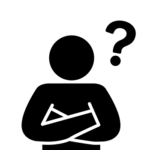
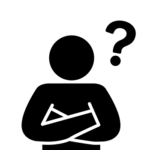
「肝臓専門医に通院しているから大丈夫では?」
肝臓専門医による定期的な経過観察は重要ですが、循環器系のリスク評価は含まれていないことがあります。総合的な健康管理のためには、循環器専門医の受診も検討してください。
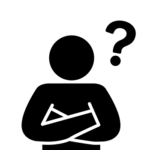
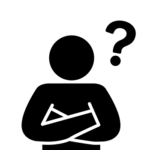
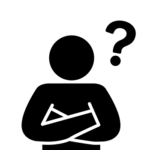
「薬を飲むと肝臓に負担がかかるのでは?」
確かに一部の薬は肝臓に負担をかける可能性はあります。しかし副作用がなく適切に管理していればスタチンなどの薬物療法はむしろ脂肪肝と動脈硬化の両方に有益であることが多いです。薬物療法のリスクとベネフィットについては、医師とよく相談しましょう。
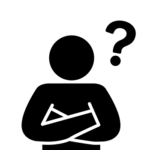
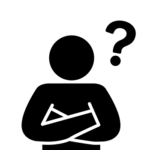
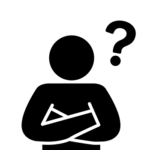
「健康診断で異常がなければ大丈夫?」
一般的な健康診断では、脂肪肝の診断はできても、動脈硬化の詳細な評価は含まれていないことが多いです。脂肪肝と診断された方は、動脈硬化の評価も含めた総合的な検査をお勧めします。
こんな目に遭わないために
循環器専門医として10年以上にわたり多くの患者さんを診てきた中で、脂肪肝と動脈硬化の関連性を痛感するケースに何度も遭遇してきました。
特に印象的だったのは、50代の男性で10年以上前から健康診断で脂肪肝を指摘されていましたが、「肝機能値は正常だから」と放置されていたようでした。ある日、突然の胸痛があり当クリニックを受診され、心電図では狭心症を示唆する変化があり総合病院に紹介しました。そこではすべての冠動脈の狭窄や閉塞が見つかりました。バイパス手術をすることになってしまった方がいました。現在当院に通院されていますが、もっと早く受診をしていたらよかったと後悔の念をおっしゃられます。
実際そんなことになっていても肝臓の状態は軽度の脂肪肝にとどまっていて、心臓以外の血管にも広範囲に動脈硬化が進行していました。「脂肪肝だけだと思っていたのに、なぜ血管がこんなに悪くなっているのか」という言葉がズシっと胸に響きます。
このケースから言えることは、脂肪肝は「肝臓だけの問題」ではなく、全身の血管の健康状態を反映する「窓」のような役割を果たしているということです。
今すぐ行動を!
健康診断で脂肪肝と言われたら
- かかりつけ医に相談する:脂肪肝の診断について話し、循環器系の評価も含めた総合的な検査を提案してもらいましょう。
- 循環器専門医の受診を検討:特に他のリスク因子(高血圧、高コレステロール、糖尿病、喫煙、家族歴など)がある場合は、積極的に循環器専門医を受診しましょう。
- 定期的な検査を受ける:脂肪肝と診断された場合は、半年から1年に一度の頸動脈エコー検査やABI検査などを検討しましょう。
まとめ
「脂肪肝」という診断は、単なる肝臓の問題ではなく、全身の血管の健康状態を反映する重要なサインです。放置すれば、心筋梗塞や脳卒中などの命にかかわる循環器疾患のリスクが高まります。
脂肪肝と診断された場合は、肝臓専門医だけでなく循環器専門医も受診し、動脈硬化のリスク評価を含めた総合的な検査を受けることをお勧めします。そして、食事・運動・禁煙・節酒などの生活習慣の改善に取り組むことで、脂肪肝と動脈硬化の両方を改善することができます。
以上
参考文献
- Targher G, et al. “Non-alcoholic fatty liver disease and risk of future cardiovascular events among type 2 diabetic patients.” Diabetes. 2005;54(12):3541-3546.
- Adams LA, et al. “The natural history of nonalcoholic fatty liver disease: a population-based cohort study.” Gastroenterology. 2005;129(1):113-121.
- 日本肝臓学会. “NAFLD/NASH診療ガイドライン2020.” 2020.
- Athyros VG, et al. “The use of statins alone, or in combination with pioglitazone and other drugs, for the treatment of non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis and related cardiovascular risk.” Curr Vasc Pharmacol. 2012;10(5):614-620.
- Bhatia LS, et al. “Non-alcoholic fatty liver disease: a new and important cardiovascular risk factor?” Eur Heart J. 2012;33(10):1190-1200.
- 厚生労働省. “令和元年国民健康・栄養調査報告.” 2020.
- Sookoian S, Pirola CJ. “Non-alcoholic fatty liver disease is strongly associated with carotid atherosclerosis: a systematic review.” J Hepatol. 2008;49(4):600-607.
- 日本循環器学会. “動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版.” 2022.
- Ekstedt M, et al. “Long-term follow-up of patients with NAFLD and elevated liver enzymes.” Hepatology. 2006;44(4):865-873.
- Patil R, Sood GK. “Non-alcoholic fatty liver disease and cardiovascular risk.” World J Gastrointest Pathophysiol. 2017;8(2):51-58.
- Byrne CD, Targher G. “NAFLD: a multisystem disease.” J Hepatol. 2015;62(1 Suppl):S47-64.
- VanWagner LB, et al. “Association of nonalcoholic fatty liver disease with subclinical myocardial remodeling and dysfunction: A population-based study.” Hepatology. 2015;62(3):773-783.
- 国立国際医療研究センター. “脂肪肝疾患の長期予後に関する研究報告.” 2018.
- 日本動脈硬化学会. “動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療ガイド2018年版.” 2018.
- 山本匡介, 他. “非アルコール性脂肪肝疾患と心血管イベントの関連についての前向きコホート研究.” 日本消化器病学会雑誌. 2016;113(6):985-992.